下肢の痛みをかかえる高齢者に合った歩行補助具の高さとは?
歩行器やシルバーカーは、高齢者の歩行を支える補助具として広く使われています。
しかし、高さが合っていないと歩行の安定性を損ね、かえって痛みや転倒リスクが増すこともあります。
本記事では、リハビリ専門職(理学療法士)の視点から、
- 歩行器とシルバーカーの違い
- 高さが合わないと起こる問題点
- 正しい高さ調整の方法とコツ
を解説します。
歩行器とシルバーカーの違い
| 補助具 | 主な用途 | 安定性 | 適応 |
|---|---|---|---|
| 歩行器 | 室内、支持目的 | ◎高い | 強い痛み、バランス不良の方 |
| シルバーカー | 屋外、買い物併用 | △〜○ | 軽度の痛み、長距離移動時 |
ポイント:
- 歩行器は身体を支えるための医療福祉用具
- シルバーカーは移動補助+荷物運搬が主な目的
高さが合わないと起こる3つの問題
- 肘が伸びすぎる → 首・肩への負担、姿勢の前傾化
- 肘が曲がりすぎる → 上半身主導の押し歩行に
- 痛みのある下肢への荷重が偏る → 疼痛悪化や転倒のリスク
正しい高さ調整の基準
推奨基準(厚労省や理学療法士協会の目安に基づく):
- 立位で自然に腕を下ろし、肘が15~30度曲がる高さ
- グリップ位置が「大腿骨大転子」または「手関節の高さ」程度
補足ポイント:
- 靴を履いた状態で調整すること
- 痛みが強い場合は、やや高めに設定して上肢で支持を補助
実践での調整ポイント
- 歩行中の姿勢を必ず確認する(立位だけでは不十分)
- 疼痛の出現、姿勢の崩れ、歩行テンポの乱れをチェック
- 「両足で体重を支え、歩行器はあくまで補助」という意識づけが重要
よくある質問(FAQ)
Q. 歩行器の高さは自分で調整してもよい?
→ 誤った調整は逆効果になるため、専門職(PTや福祉用具専門員)に相談を。
Q. シルバーカーと歩行器、どちらを選べばよい?
→ 基本は「疼痛の強さ」「屋外か屋内か」「バランス不良の有無」で選定します。
まとめ
高齢者が安全に歩行するためには、歩行器やシルバーカーの正しい高さ調整が不可欠です。
特に下肢に疼痛がある方は、高さひとつで歩きやすさも痛みも大きく変わります。
- グリップは大腿骨大転子〜手関節あたりに設定
- 肘は軽く曲がる(15〜30度)姿勢を目安に
- 歩行中に体幹が崩れていないか確認する

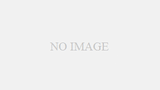
コメント