介護老人保健施設(老健)でのリハビリテーションにおいて、利用者の**在宅復帰前の「退所前訪問」**は、非常に重要な場面です。
この場面では、セラピストが適切な情報提供を行うことで、退所後のサービス事業者(訪問リハ・訪問介護・ケアマネ・福祉用具など)が安心して支援をスタートできるようになります。
この記事では、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)が「退所前訪問で説明すべきこと」と、他事業者が実際に知りたいと思っている情報について整理します。
1. 退所前訪問の目的とは?
退所前訪問は、退所後の生活環境を確認し、本人の能力と自宅環境とのギャップを埋めるための最終調整を行う場です。
特に重要なのは以下の3点です:
- 居宅での生活動作(ADL)の実現可能性を確認する
- 福祉用具や環境調整の最終確認を行う
- 家族やサービス提供者と、動作方法・支援方法を共有する
2. セラピストが説明すべきこと
① 基本動作とADLの現状
- 起き上がり、立ち上がり、移乗動作の方法と介助量
- 歩行能力(屋内・屋外、杖や歩行器の使用有無)
- トイレ動作・入浴動作の安全性と注意点
- 家事や手すりなどへの接触動作の可否(OT)
② 家庭内でのリスクと対応策
- 「滑りやすい床材」「段差」「手すり未設置」などのリスク指摘
- それに対して提案している対応策(マット敷設・スロープ設置など)
③ 使用する福祉用具の意図と使用法
- 歩行器・手すり・ポータブルトイレなどの目的と使い方
- その選定理由(例:片麻痺・膝痛で安全に歩行させたい など)
④ 家族の支援可能性と限界
- 誰が支援するか、どの時間帯に介助が必要か
- 無理のない介護の提案(ベッド移乗をヘルパー介助に切り替えるなど)
3. 他事業者が「本当に知りたい」こと
以下は、訪問リハ・訪問介護・ケアマネ・福祉用具事業者からの声として多いものです。
✅ 日常生活での「具体的な動作レベル」
- 「実際にトイレに行くとき、どこまで介助が必要か?」
- 「杖で歩くと言うが、ふらつきはどれくらいあるのか?」
→【対策】写真や動画、観察チェックシートを活用した共有が有効。
✅ 安全に介助するためのコツ
- 「立ち上がり時にどちら側から介助すべきか?」
- 「引っ張られるとバランスを崩すタイプか?」
→【対策】セラピストが現地でデモンストレーション付きで説明できるとベスト。
✅ 使用する用具と設置位置の明確な指示
- 「この手すりはどこに設置予定か?」
- 「ポータブルトイレはどの高さが最適?」
→【対策】事前にスケール写真+設置指示図などを持参しておくと親切。
4. 退所前訪問を成功させるためのポイント
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| ✅ 準備が9割 | 本人の動作能力、生活動線、用具使用方法を事前に整理しておく |
| ✅ 「説明」よりも「共有」 | 他事業者の目線で話す/質問に答えるスタンスが大事 |
| ✅ 多職種で参加する | セラピスト+支援相談員やケアマネの同席が望ましい |
5. まとめ
退所前訪問でセラピストが担うべき役割は、「訓練の成果報告」ではなく、「在宅生活を安心して始められるための橋渡し」です。
他事業者が知りたいのは、
「この人は、安全にどこまでできるのか?どう関われば安心なのか?」
という現実的な情報です。
セラピストとして、自分の言葉で伝えられるように準備しておきましょう。

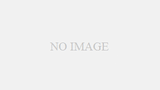
コメント