歩行器の「種類別の使い分け」、できていますか?
歩行器は高齢者の移動を支える重要な福祉用具です。
しかし、一口に歩行器といっても、種類によって適応や使い方が大きく異なります。
適切な歩行器を選ばないと、かえって転倒のリスクが増えたり、歩行が不自然になることも。
本記事では、理学療法士の視点から
- 歩行器の種類別の特徴
- 適応の違いと選定のポイント
- よくある選定ミスとその対策
をわかりやすく解説します。
歩行器の主な種類と特徴
以下の3タイプが、現場でよく使われる歩行器の分類です。
① 固定型歩行器(標準型)
特徴:
- 支持基底面が広く、非常に安定性が高い
- 使用時は本体を持ち上げて前に出す必要がある
適応:
- 両下肢に疼痛や筋力低下があるが、上肢筋力は十分にある方
- バランス能力が低下しており、安定性を優先したい方
- 室内移動が主な目的の方
注意点:
- 本体を持ち上げる必要があるため、上肢の筋力や理解力が必要
- 歩行速度はゆっくり
② 交互型歩行器(交互運動型)
特徴:
- 左右が別々に動く構造で、自然な歩行パターンに近い
- 持ち上げなくても、交互に本体を前に出せる
適応:
- 軽度のバランス障害があり、歩行パターンを自然に保ちたい方
- 固定型より軽く、扱いやすさを求める方
注意点:
- 同期が必要なため、認知機能や理解力が不十分だと扱いにくい
- 支持性は固定型よりやや劣る
③ キャスター付き歩行器(前輪型・四輪型)
特徴:
- キャスターが付いており、持ち上げなくても滑らせるように移動できる
- 前輪のみ、または全輪にキャスターが付くタイプがある
適応:
- 上肢筋力が弱い/持ち上げ動作が困難な方
- 膝や股関節に疼痛があり、滑らせる動作の方が楽な方
- 屋外や廊下などの長距離歩行が必要な方
注意点:
- 速度が出やすく、制御が不安定になりやすい
- ブレーキ付きでないと、坂道や傾斜で危険
歩行器選定のチェックポイント
歩行器の種類を選ぶ際は、以下の5点を評価することが重要です。
| 評価項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 疼痛の有無・部位 | 歩行に支障が出ているか? |
| 筋力・握力 | 上肢で支持できるか? |
| バランス能力 | 安定して立位・歩行できるか? |
| 認知機能 | 歩行器の使い方を理解できるか? |
| 利用環境 | 室内 or 屋外/段差・傾斜の有無 |
よくある失敗例と対策
❌ 失敗例1:キャスター付き歩行器を選んだが、速度が出すぎて転倒した
→ 対策: 上肢での制御が難しい方には、固定型や前輪のみのタイプを検討
❌ 失敗例2:固定型を使っていたが、上肢の疲労で途中で歩けなくなった
→ 対策: 握力や腕の疲労を考慮し、交互型またはキャスター付きに変更検討
❌ 失敗例3:認知機能の低下があるのに、交互型を選んで混乱してしまった
→ 対策: 動作が単純な固定型や、ブレーキ付きキャスター型へ切り替え
まとめ
歩行器は種類によって特性が大きく異なり、その人の状態に合わせた選定が非常に重要です。
- 固定型:最も安定性が高く、室内や重度の疼痛に向く
- 交互型:自然な歩行パターンを重視したい方に
- キャスター付き:上肢負担を減らしたい方、長距離移動に便利
適応を誤ると、かえって転倒や歩行困難につながるため、必ず専門職による評価と調整を行うことが望ましいです。
著者プロフィール
こうへい|理学療法士・運動器認定PT・主任
- 理学療法士歴9年(療養病院3年・回復期3年・老健3年)
- 現在は老健でリハ主任を務め、介護職や家族向けに「安全な介助方法と選定のコツ」を発信中

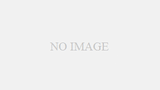
コメント